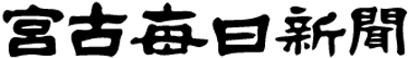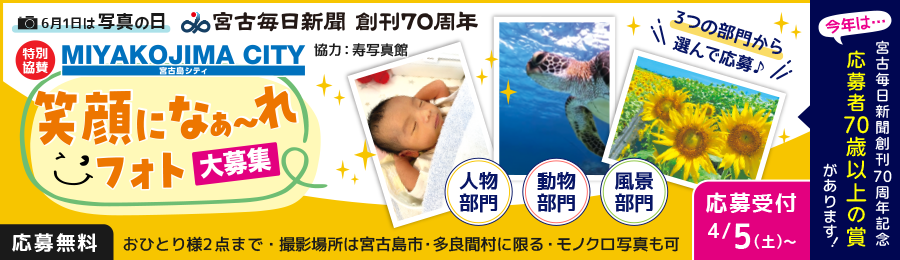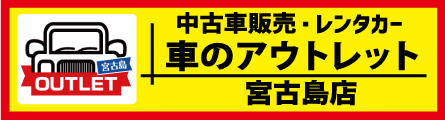漂着ごみ「国策で除去を」/防衛大名誉教授の山口氏
発泡スチロールが大量
動植物生態系への影響懸念
宮古島や八重山の海岸で漂着ごみの調査を長年行う防衛大学名誉教授の山口晴幸氏(70)が18日、本社で調査結果を明らかにした。今回の調査では、漁業用ブイやトレイに使用される発泡スチロールの大量漂着が深刻化。有害化学物質の吸着性が高いため、動植物生態系に甚大なリスクを与えるという。山口氏は「ボランティアによる清掃活動には限界がある。国が『特定監視海岸域』を設定し、国策として除去や処分体制の強化を図ることが求められる」と警鐘を鳴らした。
山口氏は1998年から宮古・八重山などでの漂着ごみ調査を開始。今回は3月15日~4月17日までの34日間かけて、宮古と八重山などの7島48海岸(調査距離28・28㌔)で実施した。
漂着ごみの大半を占めるのは、中国製のごみで依然増加傾向にあるという。韓国製や台湾製に加え、ベトナム製、マレーシア製のペットボトルも目立つようになってきた。
調査では30㌢以上の発泡スチロールをカウントし、宮古は9海岸で計4560個が確認された。最多は池間島灯台付近海岸(170㍍)で1385個も流れ着いていた。1㌔当たりでは2141個となり、八重山の約3倍という高い数字となっている。
発泡スチロールは隙間が多く、漂流過程で有害化学物質を吸着しやすい性質を持つ。小片化しやすいため、大きさが5㍉以下のマイクロプラスチックの供給源になっており、海岸に生息する生物が誤飲する可能性が高くなる。
山口氏は「マイクロプラスチックを口にした小動物は、生態系で上にいる鳥や魚に食べられる。それがいずれ人間に戻ってくる。『ブーメラン汚染』だと言える」と強調した。
また、これらの問題を対応するには、海岸線を管理する行政機関に、漂着ごみを専属で対応する部署の創設が必要だと訴えた。