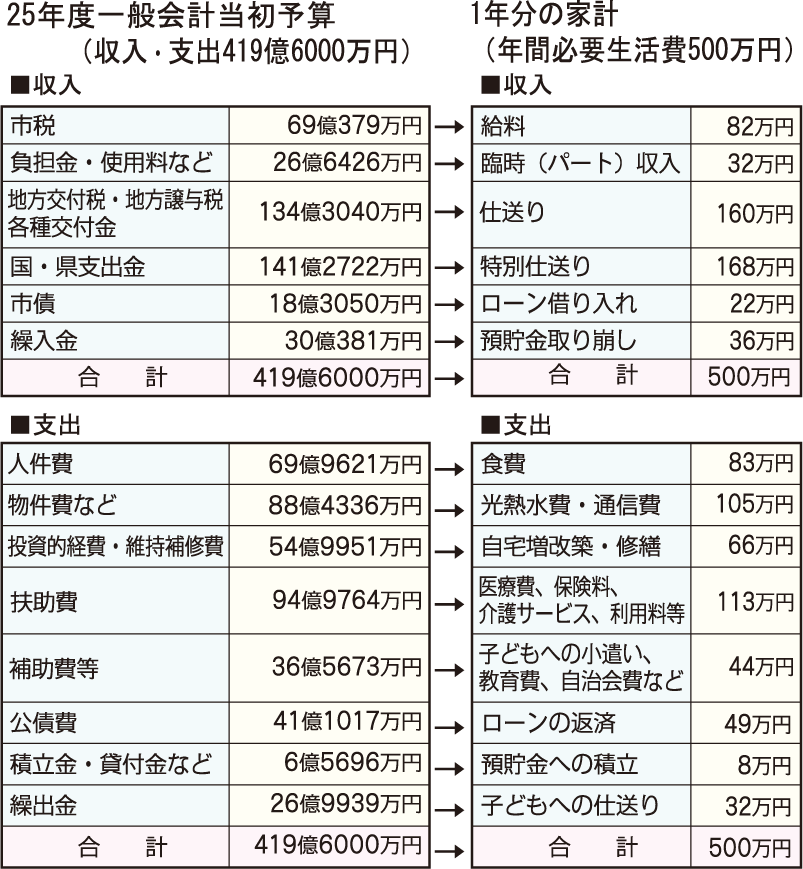偏見、差別なき社会を/ハンセン病市民学会分科会
「家族訴訟」原告が訴え
ハンセン病市民学会の第15回総会・交流会in宮古2日目は20日、宮古南静園で分科会を開いた。「家族分科会」ではハンセン病家族訴訟の原告が偏見、差別によって今も癒えることがない心の傷を吐露。「家族被害がなかったということにはしてほしくない。(6月28日の熊本地裁判決が)偏見や差別をなくす第一歩になると思う」と語った。
はじめに弁護団が裁判の経過を報告した。原告ではない家族からの問い合わせは今もあるとし、「背後には裁判をすれば『また被害を受けるのではないか』とおびえる家族が多いということがある」と指摘し、偏見が生み出した社会的差別構造の根深さを強調した。
その上で「(判決は)被害の回復に向けて社会的な施策をつくる一つのきっかけになる」と訴えた。
この後、原告による報告があった。関西在住の原告は、父親がハンセン病に罹患(りかん)したことで周囲にいじめられた過去を赤裸々に証言した。偏見、差別で家族も分断されたといい、結婚をしたときも「相手に父の病気のことを言うことができなかった」と打ち明けた。
裁判については「私たち家族も、厳しい偏見や差別の中で生きなければならなかったことをどうか分かってほしい」と話した。
沖縄在住の原告も子供のころに親のことでいじめられた過去を語った。「親の病気のことを知られると周囲の目は冷たくなった」と振り返り、大人になった今も療養所やハンセン病の単語を聞くと「びくっとしてしまう自分がいる」と癒えない傷を明かした。堕胎にも触れ、「生まれる前から差別を受けてきた人がいるんです。家族が受けた被害をなかったことにはしてほしくない」と話した。
パネルディスカッションでは弁護士の徳田靖之さんをコーディネーターに埼玉大学名誉教授の福岡安則さん、原告団の副団長、弁護士の小林洋二さん、大槻倫子さんがそれぞれの立場から提言し、参加者が家族裁判の重要性を共有した。
最後に徳田さんは「判決は大きな一歩になるが、あくまでも一歩だ。差別と偏見の一掃に向けた大きな闘いにつなげよう」と持続的な回復運動を呼び掛けた。
この日は家族訴訟と、資料館の役割を考える分科会が同時進行で行われた。ハンセン病国賠訴訟弁護団の徳田さんや琉球大学法文学部教員の森川経剛さんによる対談ほか、園内フィールドワークなどもあった。